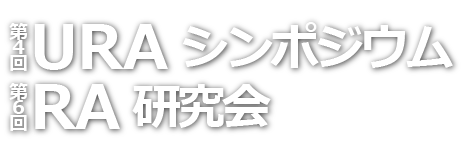
| 問合せ(主幹校):北海道大学 URAステーション 担当:江端(事務局長) |
| TEL:011-706-9581 mail:4thura_6thra@cris.hokudai.ac.jp |
参加登録の受付は、定員に達したため、 8月22日 17:00に締切らせていただきました。
たくさんのお申し込み、ありがとうございました。
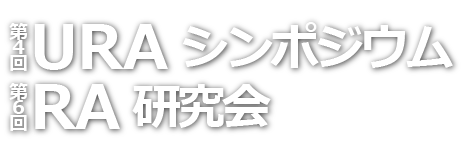
| 国際的な研究ネットワーク構築に必要な支援とは ~URA主導の事例紹介も交えて~ | |
| セッションオーガナイザー | 恒吉 有紀(エルゼビア・ジャパン株式会社) 清水 毅志・柿田 佳子(エルゼビア・ジャパン株式会社) |
| 講演者 | Anders Karlsson(Elsevier グローバル・アカデミック・リレーションズ 副社長) (英語による講演を予定しています。通訳はございません。ご了承ください。日本語の補助資料を提供予定です。) |
| 清家 弘史(東北大学 研究推進本部 ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター 特任准教授) | |
| 宇根山 絵美(岡山大学 学長特命(研究担当)リサーチ・アドミニストレーター) | |
| 恒吉 有紀(エルゼビア・ジャパン株式会社 ソリューション・マネージャー) | |
| 司会者 | 清水 毅志(エルゼビア・ジャパン株式会社 ソリューション・マネージャー) |
世界に通用する強みをもつ大学となる。そのための手段として、国際パートナー選びは必ず検討することのひとつです。最適な国際パートナーは、人的流動を促進し、高インパクトが期待できる研究活動を推進します。本セッションでは、先進的に大学主導で戦略的な国際研究ネットワーク構築の活動をされてらっしゃる大学の事例とともに、国際共著論文の動向の変化からみられる世界での国際連携のトレンドや、ネットワーク構築を支援する活動・ツールをご紹介します。
| アンデーシュ カールソン 氏 Anders Karlsson Ph.D. Vice President, Global Academic Relations Elsevier Elsevier グローバル・アカデミック・リレーションズ 副社長 |
 |
| 1992年スウェーデン王立工科大学量子工学博士号取得、NTT 物性科学基礎研究所研究員、スタンフォード大学 客員研究員を経験後、ポリテクニック工科大(フランス)、浙江大学(中国)で教鞭をとる。2001年から2011年スウェーデン王立工科大学 量子光学教授。2004年EU デカルト賞受賞。2007年~2012年スウェーデン大使館 科学技術参事官を経た後、2012年11月より現職。アジア太平洋地区を主とした戦略的な連携構築を主に担当。大阪大学未来戦略機構の顧問も務める。 | |
| 清家 弘史 氏 Hirofumi Seike, Ph.D. 東北大学 研究推進本部 ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター 特任准教授 |
 |
| 1995年東京大学理学部化学科卒業、1997年東京大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程修了、2003年The Scripps Research Institute 化学科Ph.D.コース修了。Harvard University、京都大学での博士研究員を経たのち、2011年から2013年まで英国王立化学会 (Royal Society of Chemistry) 日本事務所日本代表を務める。2013年7月より東北大学研究推進本部URAセンター特任准教授として、東北大学の研究分野における国際競争力の分析を担当。 | |
| 宇根山 絵美 氏 Emi Uneyama, Ph.D. 岡山大学 学長特命(研究担当)リサーチ・アドミニストレーター |
 |
| 2001年関西学院大学理学部化学科卒業、英国レスター大学(University of Leicester)化学科Ph.D.コース進学、Ph.D.取得。化学系企業及び大学にて研究員として勤務した後、2012年9月より岡山大学リサーチ・アドミニストレーターに着任。現在は、岡山大学の研究力強化、研究力分析、国際連携強化に取り組んでいる。 |