INFORMATION 新着情報
【ビル&メリンダ・ゲイツ財団採択】山内先生インタビュー
2024年ビル&メリンダ・ゲイツ財団(Bill & Melinda Gates Foundation)[1]の助成金に保健科学研究院 人類生態学研究室の山内太郎先生が採択されました。山内先生に、海外ファンド挑戦の動機や、そのための戦略に関するお話を伺いました。
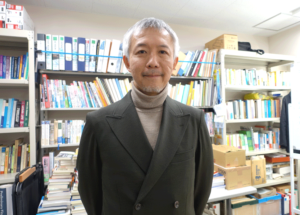
Q. 山内先生の研究について簡単にご紹介いただけますか?
人類生態学(Human Ecology)は、人類学(自然人類学、文化人類学)、地理学、生態学、医学・保健学、栄養学、人口学などを含む文系・理系の枠を超えた幅広い学際的分野です。特に本研究室では、海外、主にGlobal Southでのフィールド調査を積極的に行い、地域目線でその地域の課題の解決に貢献することを目指しています。
Q.これまでに他の海外ファンドに応募した、あるいは獲得したご経験はおありですか?
海外ファンドへの取り組みは比較的最近です。JST「戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)」[2] のAJ-CORE(Africa-Japan Collaborative Research)[3] で共同研究をしているアフリカ3か国(ザンビア、ボツワナ、南アフリカ)の研究者との連携をさらに強化するために新たな研究費の取得を考えました。また主宰する研究室(人類生態学研究室)のアフリカや東南アジアからの大学院留学生と相談し、研究室の強みを活かすには、国内の研究費よりも海外の研究費が良いのではということになり、ビル&メリンダ・ゲイツ財団の応募に至りました。
Q. ビル&メリンダ・ゲイツ財団に採択された要因は何だと思いますか?
当研究室のプロジェクトが採択された背景には、以下の点が評価されたと思います:
1.国際的な研究活動
日本、インドネシア、バングラデシュ、ザンビア、カメルーンなど、
先進国から途上国まで幅広い地域でのフィールド調査を実施。
2.具体的な課題解決を視野に入れたアプローチ
地域の文脈を考慮した仕組みづくりや製品開発などを視野に入れた
包括的な課題解決アプローチを展開。
3.学際研究及び超学際的研究の実績
過去30年間にわたり、学問分野を超えた学際研究(Interdisciplinary Study)を推進してきたことや、
総合地球環境学研究所(地球研)の大規模国際プロジェクトでアカデミア以外の地域の
多彩なステークホルダーを巻き込んだ超学際研究(Transdisciplinary Study)をおこなってきた経験が、
財団が目指すところと一致。
昨今、海外ではアカデミアに社会問題解決を求める潮流が主流となる中、今回のプロジェクトでは科研費など国内のグラントではなく、国際的なグラントの方が合っていました。
Q. お話を聞いていて、相手(資金提供機関)のことをよく調べて、戦略的に考えられていると感じました。先生が考える「海外ファンド獲得成功のカギ」とは何だと思われますか?
私たち自身も最近本格的に取り組み始めたばかりですが、海外ファンドの申請は適切な選定と準備が重要です。提案内容に合致した応募内容であるかどうかだけでなく、海外研究者との連携や人材育成という点も重要だと考えています。例えば現在進めておりますBellmont Forum[4] への申請では、代表者はザンビアの研究者ですが、申請書の作成は私たちがサポートしています。これが採択されれば、双方にとってwin-winの成果となります。
私たちは以前から、Global Southの若手研究者を支援する理念を大切にしており、ファンド申請にとどまらず、国際ジャーナルの運営や国際学会の開催も研究室で行っています。一研究室がここまで行っている例はあまりないと思います…(笑)。
Q. 助成金獲得にあたり、北海道大学内外でどのような支援や協力を受けましたか?
私の所属する保健科学研究院では海外フィールド調査は一般的ではありませんでしたが、事務の方々の建設的なサポートがとても有難かったです。また、申請書類では北海道大学が国立大学であることを証明する英語の文書などが必要で、それを準備する際には、国際部の方々にお世話になりました。このような部局や全学組織の支援によって、最終的に採択に至ったことに感謝しています。
Q. 他の研究者が海外ファンドに挑戦するためには、大学としてどのような支援が必要だと思いますか?
情報提供の充実が重要だと思います。例えば、海外ファンドの情報を一元化し、研究者が簡単にアクセスできるようにする等です。また、所属する事務部への全学からのサポート体制を整えていただくことも大切だと思います。さらに、可能であれば、研究者が課題や疑問を相談できる「お悩み相談」的な窓口の設置も役立つかもしれません。
Q. 海外助成金を獲得する上で求められる要素や姿勢は何だと感じますか?
最も重要なのはモチベーションです。私の場合、「これが取れたら、自分のやっている調査研究がもっと進む」とか「現地で立ち上げた、子どもクラブ[5] を何とか運営し、維持していかなければ」というマインドがモチベーションになっています。そして現地のステークホルダーを巻き込んだアクションリサーチによって、「実際に子どもや大人、そして地域社会が変わっていくのを実感する」という達成感が大きな原動力だと思っています。
Q. 海外助成金に挑戦する研究者に向けて、山内先生から具体的なアドバイスをいただけますか?
私自身は、国際保健学を通じてGlobal Southの地域社会におけるフィールド調査に長年取り組んできましたが、海外で研究調査活動を行わない分野から国際ファンドに挑戦する場合はハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、不採択でも失うものはなく、申請の経験が次に活かせると私は考えています。
将来的には国内の研究費と海外の研究グラントの両方を活用することが当たり前になると思います。国の方針も民間企業や海外ファンドからの資金獲得を推進する潮流を感じています。特に若手研究者には積極的に挑戦してほしいです。海外の研究者と連携して、少額の研究費でもよいので、何かチャレンジしてみることが大きな一歩になると思います。
山内先生、ありがとうございました!!今後の一層のご活躍をお祈りいたします。
[1] ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、2000年にビル・ゲイツ(Microsoftの共同創設者)とメリンダ・フレンチ・ゲイツによって設立された、世界最大級の慈善団体です。貧困や健康問題の克服を通じて、世界中の人々の生活を向上させることを目的にしています。
[2] https://www.jst.go.jp/inter/
[3] https://www.jst.go.jp/inter/program/multilateral/aj-core.html
[4] https://www.jst.go.jp/inter/sicp/country/belmont-forum.html
[5] https://www.facebook.com/DzikoLangaZMB/


